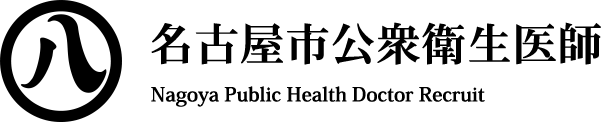公衆衛生医師の魅力 – ポイント6
全国の仲間と共同事業・研究ができる

中川保健センター 細野 晃弘
日本には北から南まで全国にある保健所ですが、仕事の内容はほぼ同一です。ところが管轄区域によっては、ある地域では対応できている事項に、こちらではどう対応すれば良いかわからない、といったことが起こります。または問題対応力を上げるためのシステムを構築するリソースがない、といったことも起こり得ます。全国保健所長会(https://www.phcd.jp/)では、そういった「困った」への対応力を上げるための研究事業を行っていて、毎年、全国の保健所から研究班員を募集しています。
私は、令和4年度から5年度にかけて、「グローバル化時代における保健所の機能強化と国際社会への貢献に関する研究」の班員でした。この研究班は外国人対応の方法をまとめていたり、感染症事例や精神障害事例で使用する各種文書を多言語化したりと、外国人対応の経験が少ない保健所には嬉しいツールを作っています。(https://www.phcd.jp/02/t_gaikoku/)
班員は、全国各地の保健所から10名ほど、それに助言者としてほぼ同数の大学教員や外国人診療に長じた開業医、国際保健協力NGOなど各界のエキスパートが加わっていました。その中で私は「国際・国内の保健衛生行政を往来できる人材の育成」を担当し、国際保健経験のある者が帰国後、そのキャリアをどのように生かしているか、また生きているのかを明らかにするため、群馬県や長崎県まで、経験者のインタビューに行きました。国際経験のある先輩の、生の経験を聞くことが大きな刺激になり、またそういう先輩の逞しさや高い問題解決能力に強く憧れを抱きました。
名古屋市の中だけで生きていれば、なかなか得られない経験です。ですが、その経験を得られる場には、手を少しのばせば届きます。全国の先輩・同志が、皆さんのチャレンジを待っています!